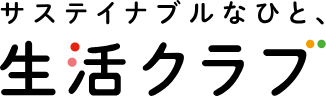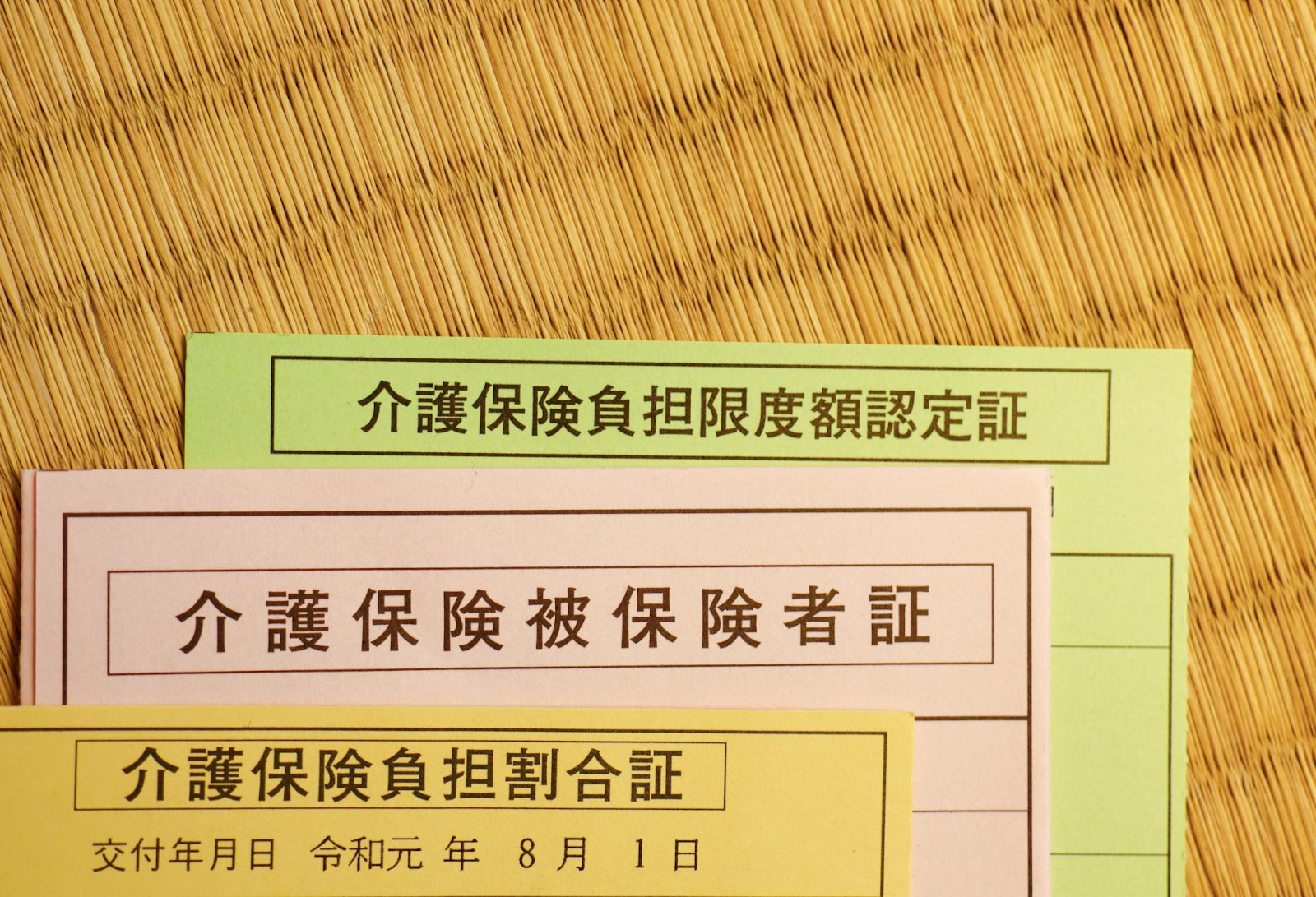
2024年の介護保険制度改定は施行時期が決定し、具体的な改定の内容や方向性についても厚生労働省より公表がされています。
介護保険制度改定は、介護保険の利用者にとっても無関係ではありません。介護保険を利用している方や、介護をしている家族の方は、2024年の改定によって介護保険制度がどのように変わるかを知っておきましょう。
今回は、2024年に介護保険制度がどのように改定されるかや、施行日がいつ頃なのかを解説します。介護保険に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
3. 2024年度介護保険制度改定|4つの視点ごとの改定ポイント
3-3. (3)良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
1.2024年介護保険制度改定の背景
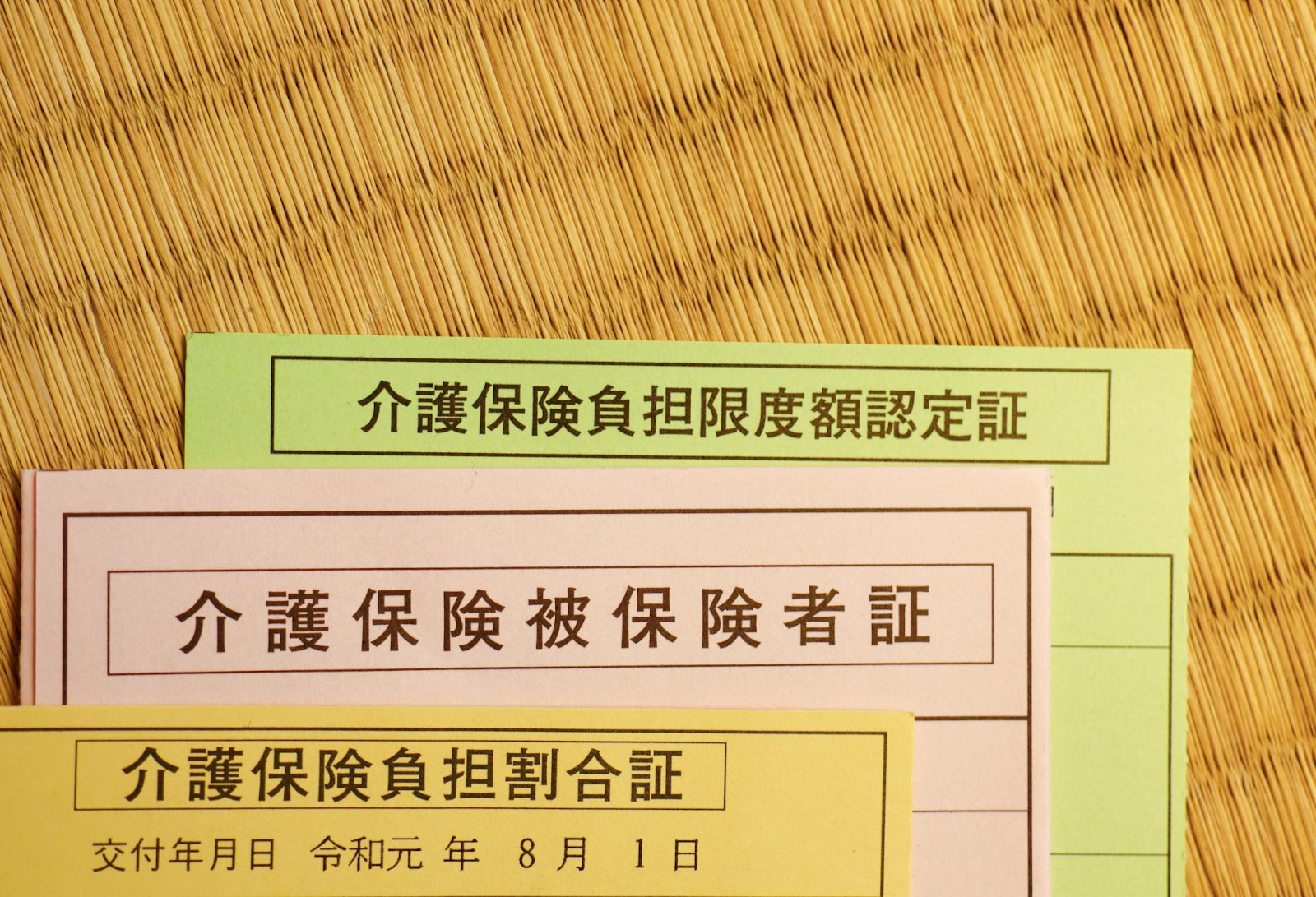
介護保険制度は、要介護認定や要支援認定を受けた方が介護サービスを受けられる制度です。介護保険制度の運営や介護サービスの提供には、国民が納めた介護保険料や税金が使われています。40歳以上の国民は、介護保険への加入が義務付けられています。
介護保険制度は2000年に施行されて以来、定期的に見直しが行われてきました。社会情勢や環境の変化に合わせた制度の見直しにより、利用者やご家族は適切なサービスを受けることができます。
2025年には人口数が多い団塊世代が後期高齢者となります。「2025年問題」に向けた2024年度の制度改定は、特に重要な法改正になるでしょう。
2.2024年度介護保険制度改定の改定率と施行日

厚生労働省は2023年12月20日、2024年度の介護報酬の改定率は引き上げの方向で決定しました。
改定の施行日はサービス種別によって異なるため、自分が利用するサービスではいつ頃に施行されるかを把握しましょう。
ここからは、2024年度介護保険制度改定の改定率と施行日を解説します。
2-1.改定率は「1.59%」引き上げ
介護報酬の改定率は「1.59%」引き上げとなりました。改定率の内訳は下記の通りです。
介護職員の処遇改善分 | +0.98% |
|---|---|
その他の改定率 | +0.61% |
「その他の改定率」は、賃上げ税制を活用しながら、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準であるとされています。
介護報酬改定による1.59%の引き上げとは別に、改定率の外枠での引き上げもある見通しです。処遇改善加算一本化による賃上げ効果や、介護施設の基準費用額増額による増収効果で、改定率の外枠での引き上げは「+0.45%」相当になります。
介護報酬改定による1.59%と、改定率の外枠である0.45%を合計すると、「+2.04%」相当の改定となる見込みです。
2-2.施行日は介護サービス種別によって異なる
2024年度介護保険制度改定の施行日は、サービス種別によって下記の2パターンに分けられています。
2024年4月に施行 | 2024年6月に施行 |
|---|---|
|
|
ただし、介護職員の処遇改善分である「+0.98%」の改定については、2024年6月1日に施行されることになっています。
3.2024年度介護保険制度改定|4つの視点ごとの改定ポイント
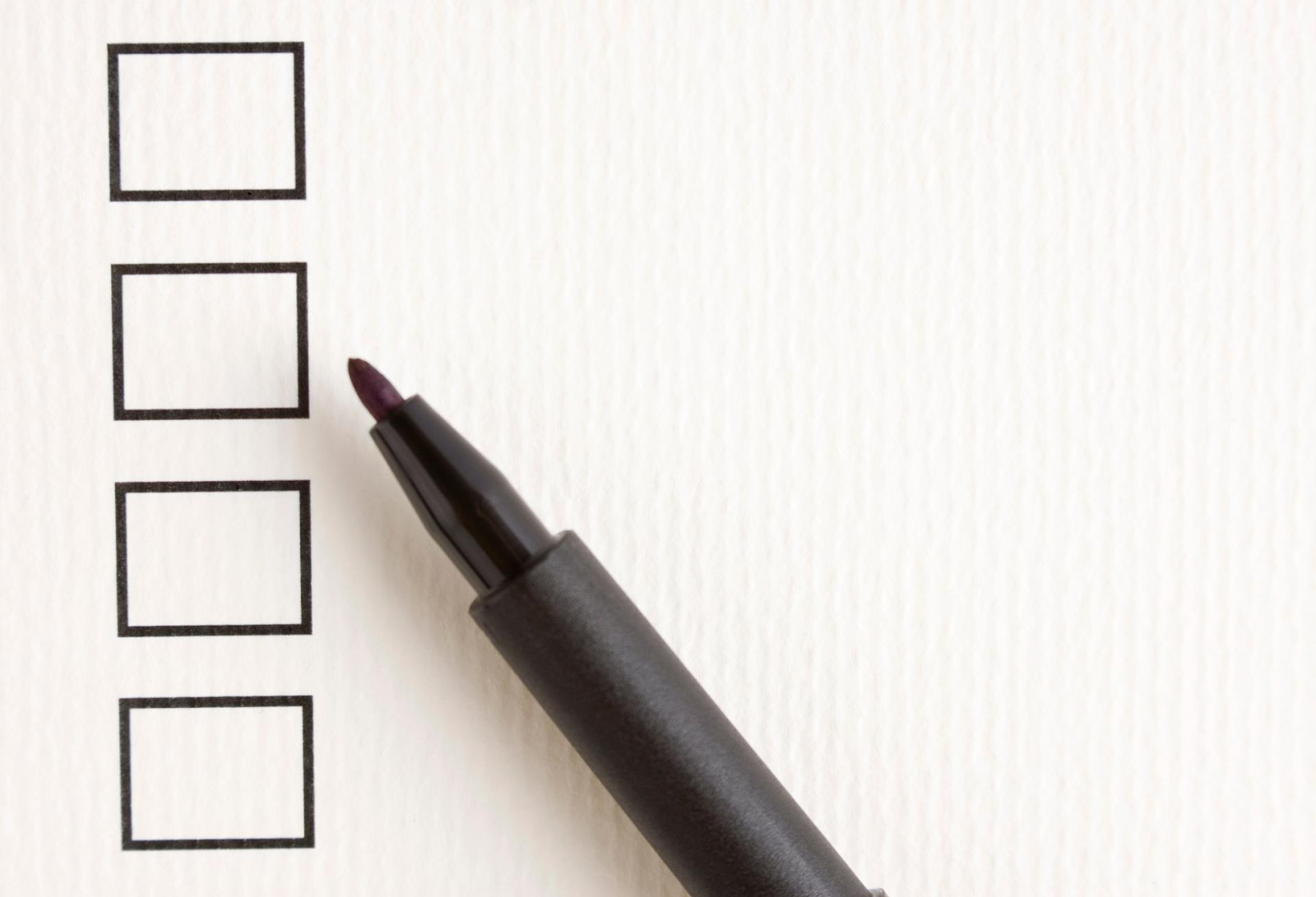
2024年度の介護保険制度改定は、下記の4つを基本的な視点として改定内容が定められています。
|
4つの視点は、現代の日本社会が迎えている介護需要の増大や、介護人材不足の深刻化に対応するためのものです。
ここからは、4つの視点ごとにおける改定ポイントを詳しく解説します。
(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告の概要」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180879.pdf)
3-1.(1)地域包括ケアシステムの深化・推進
「地域包括ケアシステムの深化・推進」では、介護を必要とする方に質の高いケアマネジメントやサービスを切れ目なく提供できることを目指しています。加えて、地域の実情に合った柔軟性を持たせ、効率的な取り組みを推進する視点です。
主な改定内容としては、下記のものが挙げられます。
居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件や、居宅介護支援事業者が介護予防支援を行う場合の要件などについて見直しがされます。
訪問介護における特定事業所加算の要件や、総合マネジメント体制強化加算の区分について見直しがされます。また、通所介護費等の所要時間の取り扱いについて、気象状況悪化などのやむを得ない事情が考慮されるようになります。
看護師や薬剤師によるケアへの加算や、医療機関による居宅介護支援の評価の見直しなどが行われます。
各種介護施設におけるターミナルケア加算や看取り体制強化の評価などについて、見直しが行われます。
高齢者施設等における感染症対応力の向上や、感染した高齢者の施設内療養についての評価が行われます。業務継続計画が策定されていない事業所への減算導入も特徴です。
虐待の発生や再発の防止ができる措置が求められるようになり、身体的拘束等の適正化も図られています。
認知症についての加算の見直しや、認知症の予防・リハビリテーションを評価する加算が設けられます。
一部の福祉用具について貸与と販売の選択制導入や、福祉用具貸与のモニタリング実施時期の明確化などが行われます。 |
(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180845.pdf)
3-2.(2)自立支援・重度化防止に向けた対応
「自立支援・重度化防止に向けた対応」では、高齢者の自立支援や重症化防止を実現するために、多職種間の連携やデータの活用を推進しています。
主な改定内容は下記の通りです。
リハビリテーションマネジメント加算や個別機能訓練加算(II)における新たな区分の設置、医療と介護の連携を推進するための各種見直しを行う内容です。 また、サービス利用者に対する口腔・栄養の管理強化や介入の充実、介護と医療関係者の連携推進といった取り組みも行われます。
通所型サービスにおける入浴介助加算の見直しや、個室ユニット型施設の管理者に対するユニットケア施設管理者研修受講の努力義務化が行われます。 介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援等評価指標と要件の見直しや、かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直しがされる点も特徴です。
厚生労働省が推進しているLIFE(科学的介護情報システム)の活用について、入力項目の見直しや加算の見直しが行われます。 特にLIFEによるアウトカム評価の充実は大きな変更点です。 排せつ支援加算や褥瘡マネジメント加算等について評価の項目が増えて、介護の質向上を図る内容となっています。 |
(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180845.pdf)
3-3.(3)良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
「良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」では、処遇改善や働きやすい職場環境づくりなど、介護人材の不足に対処する内容が盛り込まれています。
また、人員配置・勤務体制などについて、基準の見直しや明確化が行われることも特徴です。
主な改定内容は下記の通りとなっています。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が、4段階の介護職員等処遇改善加算に一本化されます。介護職員の処遇改善につながる措置を、なるべく多くの事業所が活用できるようにするための改定です。 なお、改定には1年間の経過措置期間が設けられます。
テレワークの取り扱いについての明確化や、介護ロボット・ICTといったテクノロジーの活用を推進する内容です。介護の全サービスにおいて、治療と仕事の両立ができる環境整備を進めるために、人員配置基準や報酬算定についての見直しも行われます。 また、外国人介護職員における人員配置基準上の取り扱いも見直しが行われ、要件を満たすことで就労開始直後から人員配置基準に算入できるようになります。
介護サービスの管理者の責務を明確化した上で、管理者が責務を果たせる場合であれば、兼務できる事業所の範囲が同一敷地内でなくても差し支えなくなります。 また、訪問看護等における24時間対応の体制について、見直しや評価区分の新設が行われます。 他にも、退院時共同指導の指導内容が文書以外で提供可能になるなど、柔軟なサービス提供につながる内容です。 |
(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180845.pdf)
3-4.(4)制度の安定性・持続可能性の確保
「制度の安定性・持続可能性の確保」では、介護保険制度の安定性と持続可能性を確保し、全世代が安心して利用できる制度の構築を目指しています。
主な改定内容は下記の通りです。
訪問看護における同一建物減算について、利用者の一定割合以上が同一建物等居住者である場合に対応した新たな区分を設け、さらに見直しも行います。 また、短期入所生活介護の長期利用が増加している状況を踏まえ、施設入所と同等の利用形態となる場合には、施設入所の報酬単位との均衡が図られるようになります。
運動器機能向上加算が廃止され、基本報酬への包括化が行われます。他にも、認知症情報提供加算・地域連携診療計画情報提供加算・長期療養生活移行加算が廃止されます。 報酬の見直しでは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬と、経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲について見直しが行われます。 |
(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180845.pdf)
4.2024年介護保険制度改定で見送られた2つの事項

介護保険制度改定に向けて政府が提言していた事項のうち、すでに2つの事項について見送りが決定しています。2024年度の改定で見送りになった事項は、2027年度の改定で結論が出される予定です。
ここでは、2024年度の介護保険制度改定で見送られた2つの事項について、概要と見送りの理由を解説します。
4-1.要介護1~2における総合事業への移行
要介護1~2における総合事業への移行は、要介護1・2の訪問介護や通所介護などの介護サービスを総合事業にして、地域や民間企業と連携する構想です。
総合事業への移行には、サービスの質の低下や事業所の撤退などの懸念もあることや、世論の反対が大きかったこともあり、2024年度は見送りが決定しました。
4-2.ケアプランの有料化
2024年度の介護保険制度改定では、ケアプランの有料化も見送られました。
現在、在宅サービスにおけるケアプランの作成は10割保険負担のため利用者負担はありません。一方で、施設サービスではケアマネジメント費用を利用者が負担していることから、政府は公平性を保つために有料化を提言していました。
しかし、「利用者やご家族からの要求がエスカレートしかねない」「利用料管理などの業務負担が増える」などの反対意見が多く、2027年度の改定に持ち越されました。
まとめ
2024年度の介護保険制度改定では、介護報酬の改定率は1.59%引き上げとなりました。
介護報酬の改定以外にも、介護保険制度改定には多くの改定ポイントがあります。介護サービスの利便性向上や、増加する介護ニーズに対応するための改定内容が多いものの、サービス利用に影響する内容もあるため確認しておきましょう。
「要介護1~2における総合事業への移行」「ケアプランの有料化」は、2024年度の介護保険制度改定では見送りとなりました。しかし、次期の改定時には再び議論される可能性が高く、介護サービスの利用者は注視が必要と言えます。