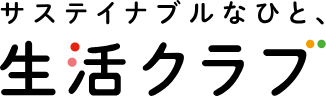共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「新生活のリスクに備える」です。
新社会人に必要なリスクに備える保障をはじめ、入園入学を迎える方へのおすすめ保障、住まいの保障など掲載しています。
掲載記事はこちら:たすけあいカタログ2021年2月号
このたびの地震により被害を受けられた皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
CO・OP共済・生活クラブ共済ハグくみでは、災害救助法が適用された地域※に居住するご契約者さまを対象に、共済掛金の払込猶予期間を延長(最長6ヶ月間)するお取り扱いをさせていただきます。
【CO・OP共済 にご加入の方】
掛金振替猶予のお問い合わせ⇒ 0120-50-9431 9時~18時(日曜日定休日)
詳細は以下の専用ホームページよりご確認ください。
CO・OP共済HP:災害救助法適用地域の共済掛金払込に関する特別のお取り扱いについて
【生活クラブ共済ハグくみ にご加入の方】
共済掛金の払込猶予期間延長の内容
契約者である組合員の方から連絡していただければ、共済掛金の払い込み期限を最長6か月延長いたします。
ご希望の方は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。
生活クラブ共済事務局⇒ 0120-220-074 受付時間:9時~17時(月~金※祝日含む)
※適用地域一覧(2021年2月14日7時時点)
《福島県》
福島市(ふくしまし)
郡山市(こおりやまし)
白河市(しらかわし)
須賀川市(すかがわし)
相馬市(そうまし)
南相馬市(みなみそうまし)
伊達市(だてし)
本宮市(もとみやし)
伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち)
伊達郡国見町(だてぐんくにみまち)
岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち)
大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)
双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)
双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)
双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)
双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち)
相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)
前回のコラムで、給与所得者は源泉徴収制度になっているので、確定申告は原則不要と書きました。しかし下記の場合は、確定申告が義務付けられていますので注意が必要です。
【給与所得者でも確定申告しなければならない場合】
1.給与の年収が2,000万円を超えるとき
⇒年収が2,000万円を超えると、年末調整の対象外となるため確定申告が必要。
2.給与所得以外の所得金額が20万円を超えた時
⇒年末調整で精算できるのは、勤務先が支払っている給料のみ。それ以外の副業収入が20万円超ある場合は、確定申告が必要。
3.給与を2か所以上からもらった時
⇒年末調整は、一か所の勤務先しかできないので、すべての給与を合算して、所得税を確定するために確定申告が必要。
これまで多くの日本企業では、就業規則で「副業禁止」を定めているところが一般的でした。しかし国は「働き方改革実行計画」(平成29年3月)により、副業や兼業の普及促進を図っています。最近では、少しずつですが「副業解禁」する会社も出てきています。働き方が変われば、税金の手続きも変わります。これまで全て勤務先任せだった給与所得者でも、確定申告が必要な人が今後は少しずつ増えてくることが予測されます。税制の基本を理解しておきましょう。
以上
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
NPO法人Wco.FPの会は、おもに生活クラブ生協の組合員対象のライフプラン講座の企画、講座の講師派遣、および個人相談の三つの事業を中心に活動しています。
ライフプラン講座メニュー:こちら
個人相談は、生活クラブ共済連ホームページよりお申込みができます。
保障の見直し個人相談:こちら
税金は、国を維持し、社会で生活していく上でかかせないものです。日本国憲法第30条で、「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」とあります。納税は、「勤労の義務」「教育の義務」と並んで、国民の三大義務の一つです。もし税金を正しく納めなかった場合は、ペナルティが課されるだけでなく、場合によっては刑事罰に処されることもあります。
本来税金は、自らが税務署へ正しい申告を行い、税額を確定させ、自ら納付する「申告納税制度」が基本です。具体的には、個人事業主であれば、毎年1月から12月までの収入から経費などを差し引いて税額を計算します。それを翌年2月~3月にかけて確定申告をして納税します。
しかし公務員や会社に勤めて給料をもらっている人(給与所得者)は、「申告納税制度」ではなく「源泉徴収制度」になっています。これは勤務先が所得税を毎月源泉徴収し、1年の終わりに年末調整をして納税が完了するしくみです。勤務先が一連の手続きを行うため、確定申告は原則不要です。
このコラムでは、原則的に手続きが不要な給与所得者の確定申告についてお知らせします。主に申告することで払いすぎた税金が戻ってくる例を取り上げます。手続きをしないと税金は戻ってこないので、申告した方が良い例を知っておくと役立ちます。
以上
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
NPO法人Wco.FPの会は、おもに生活クラブ生協の組合員対象のライフプラン講座の企画、講座の講師派遣、および個人相談の三つの事業を中心に活動しています。
ライフプラン講座メニュー:こちら
個人相談は、生活クラブ共済連ホームページよりお申込みができます。
保障の見直し個人相談:こちら
「教育費をどうしようかな」と思った時にまず読む本(日本経済新聞社、竹下さくら著)
「教育費」は、人生の三大資金(※1)のひとつで、家計負担が重い支出です。公的な制度により高校授業料無償化、幼児教育・保育の無償化、さらに返済不要な給付型奨学金の創設などにより、少しずつ負担は和らいでいるようにも見えます。しかしまだまだ家計にずしりと響いているのが現状です。なぜなら一番お金がかかる大学の教育費の負担は、相変わらず重いままだからです。
本書では、進路によって実際にかかる金額、教育資金の準備方法、資金を準備できなかった時のための助成制度や奨学金制度などが事例とともに紹介されています。特に資金の準備方法では、預金や学資保険だけでなく、投資で増やすことも紹介されています。さらに投資で利用できるお得な制度として、NISAやiDeCo(※2)についても理解が深まるので、家計全般の見直し、資産運用まで合わせて学べる内容になっています。
子どもの教育については、親の「収入格差」と「情報格差」があると言われています。収入格差をなくすのは困難ですが、情報格差は小さくすることができます。『「教育費をどうしようかな」と思った時にまず読む本』というタイトル通り、できればお子さんが小学生くらいまでの時期に一読し、教育費の備えていくことをおすすめします。
(※1)人生の三大資金:教育資金・住宅資金・老後資金
(※2)NISA:少額投資非課税制度、iDeCo:個人型確定拠出年金、ともに運用にあたり税制上優遇されている制度)
以上
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
NPO法人Wco.FPの会は、おもに生活クラブ生協の組合員対象のライフプラン講座の企画、講座の講師派遣、および個人相談の三つの事業を中心に活動しています。
ライフプラン講座メニュー:こちら
個人相談は、生活クラブ共済連ホームページよりお申込みができます。
保障の見直し個人相談:こちら
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「コロナ禍でのたすけあいを支える組合員の力」です。
生活困窮者を支援する団体への助成、若者おうえん基金への継続的な寄付活動、生活クラブグループの福祉事業データ2019年度報告など掲載しています。
掲載記事はこちら:たすけあいカタログ2021年1月号
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「家計にやさしく、福祉もひろげる「共済」」です。
1年間の家計の振り返りやワンポイントアドバイス、生活クラブ福祉事業基金の寄付募集など掲載しています。
掲載記事はこちら:たすけあいカタログ2020年12月号
CO・OP共済2020年度の制度改定内容についてご案内します。
1.手術共済金請求における提出書類簡素化基準の見直し
・2020年9月請求受付分より、診断書がなくても請求できるケースが増えました。
詳細ページ:こちら
2.個人賠償責任保険 制度改定
・物理的な損害を伴わずに、電車等が運行不能になったことで発生する損害賠償への保障を追加しました。
・住宅に関する事故について、保障の対象となる住宅の範囲を広げました。
詳細ページ:こちら
保障内容:個人賠償責任保険
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「知っておきたい、くらしに身近な税金・年金」です。
給与所得者の年末調整に関する情報のほか、CO・OP共済保障内容の確認チェック、ペット保険など掲載しています。
掲載記事はこちら:たすけあいカタログ2020年10月号
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「多様な人々の共生を支えるたすけあい」です。
オンラインセミナー「自分で選ぶ高齢期の暮らし方」参加者募集、生活クラブの3つの寄付活動、第11回生活クラブ共済連通常総会報告、生活クラブ共済ハグくみ取組み開始7周年などを掲載しています。
掲載記事はこちら:たすけあいカタログ2020年9月号
「マイページお手続きでOnlineたすけあい ~CO・OP共済 医療従事者応援プロジェクト~」
実施期間2020.7.22~10.20
当プロジェクトは新型コロナウイルスと闘っている医療従事者へ、全国の組合員から寄せられた応援する想いを寄付金という形で届けることを目的としています。
CO・OP共済の契約者向けWebサービス「共済マイページ」の利用登録または「共済マイページ」上で指定の手続きを行なっていただいた件数に応じ、日本医療福祉生活協同組合連合会へ寄付を実施します。
共済マイページは、パソコン・スマートフォンを利用して、《あいぷらす》割戻金のご請求、住所変更などのお手続きやご契約内容の照会が行なえるサービスです。
寄付金は、防護服やフェイスシールドの購入等に活用されます。
・実施期間:2020年7月22日~2020年10月20日
・寄付金額:対象のお手続き件数(1件)につき50円
※コープ共済連から対象のお手続きを行った件数に応じて寄付を行ないます。
※お手続きを行なっていただいた方に直接寄付金をご負担いただくものではございません。
●プロジェクトの詳細:こちら
●共済マイページ利用案内・登録:こちら
●スマートフォンから共済マイページ利用案内・登録(QRコードより):こちら
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「賠償保障と自分自身のケガの備え」です。
自転車事故への備えや、生活クラブ共済ハグくみのインターネット申込み開始などを掲載しています。
掲載記事はこちら⇒たすけあいカタログ2020年8月号
生活クラブ共済ハグくみ インターネット申込みが始まりました。
7月31日(金)より、インターネットでも申込みできるようになりました。
「生活クラブ共済ハグくみ」は、たすけあいの消費材で、生活クラブオリジナルの医療保障です。
◆ネット申込みはこちら:ハグくみネット申込み
◆詳しい保障内容はこちら:ハグくみページ
このたびの令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
CO・OP共済にご加入の組合員の皆様へのご案内
上記の災害によりケガをされ、入院、通院をされた場合は、共済金の支払いがあります。また、住宅や家財に被害があった場合、被害の程度により共済金等があります。
CO・OP共済《たすけあい》(ジュニア20コースを除く)にご加入の場合は住宅災害共済金、CO・OP火災共済・自然災害共済にご加入の場合は「風水害等共済金」をお支払いできる場合があります。
・詳しくはコープ共済連ホームページをご覧ください。
コープ共済連HP⇒こちら
共済金のご請求は、以下のフリーダイヤルへご連絡ください。
■コープ共済センター
0120-08-9431
受付時間:9:00~18:00 月~土(祝日含む)
(ご注意)
・ご加入のCO・OP共済の内容によっては、保障がない場合もあります。
・混み合ってつながりにくい時がありますのでご了承ください。
■火災共済、自然災害共済に加入の方
0120-6031-43
◆共済事故(住宅損害)の受付に関するご連絡 ⇒ ご用件番号【0】をご選択ください。
CO・OP火災共済事故受付センター 24時間365日受付可能
◆現在のご契約に関するお問い合わせ ⇒ ご用件番号【1】をご選択ください。
CO・OP火災共済コールセンター 9:00~18:00 月~土(祝日含む)
災害救助法適用地域の共済掛金払込に関する特別のお取り扱いについて
(※2020年7月29日更新)
・詳しくはコープ共済連ホームページをご覧ください。
コープ共済連HP ⇒こちら
生活クラブ共済連は、2020年6月22日に、第11回通常総会を開催しました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、会員生協の代議員(定数250名)は、書面議決を中心とした参加となり、2019年度活動報告と決算報告、2020年度活動方針と予算等が提案され、全ての議案が賛成多数で可決され終了しました。
詳細はこちら⇒ 生活クラブ共済連_ 第11回通常総会のご報告
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「たすけあいの消費材と福祉活動報告」です。
生活クラブ共済ハグくみの利用者の声や、生活クラブ福祉事業基金助成報告などを掲載しています。
掲載記事はこちら⇒たすけあいカタログ2020年7月号
ライフプラン講座の開催方法に、WEBツール*を用いたオンライン開催を新たに追加しました。
※パソコンやスマートフォン・タブレット端末から、映像と音声を使って参加できます。
〈対象の講座〉
オンライン開催が可能な講座は定番講座のみです。
講座メニューはこちら:定番講座
ライフプラン講座の参加およびオンラインの参加を希望するかたは、ご加入の生活クラブへお問い合わせください。
各地の生活クラブ:こちら
〈ご注意ください〉
ご自宅からオンラインで参加するかたは、インターネット回線や契約プラン(定額制)などの通信環境を事前にご確認ください。
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「2019年の台風による災害の概況と備える共済」です。
昨年の台風によるおもな被害状況や、共済による自然災害への備えについて掲載しています。
また、組合員向けのコープ共済インターネット加入開始や、生活クラブ共済ハグくみホームページで楽しめるコンテンツをご紹介します。
掲載記事はこちら⇒たすけあいカタログ20年6月
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「生活クラブの福祉・たすけあい8原則と実際の活動」です。
実際の活動のなかから今回は、「リーディングサービス」「ライフプラン講座」をピックアップしました。
掲載記事はこちら⇒たすけあいカタログ20年5月
日頃よりCO・OP共済をご利用いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けられている方々におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。また、罹患されている方々におかれましては、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
今回、「新型コロナウイルス感染症」の拡大に伴う政府からの緊急事態宣言に伴い、コープ共済センター(コールセンター)の営業について、開始および終了時間を30分ずつ短縮することになりました。ご不便をおかけいたしますがご理解賜りますようお願い申し上げます。
(2020年5月7日更新)
政府からの緊急事態宣言の期間延長を受けて、コープ共済センター(コールセンター)の営業時間短縮となる期間も5月31日(日)まで延長となります。営業時間短縮となる期間は4月25日(土)から5月31日(日)までを予定していますが、緊急事態宣言の動向により対象期間が延長する場合は、ホームページ上にてご案内いたします。
<短縮後の営業時間について>
共済金のご請求に関する窓口:0120-80-9431
9:30~17:30(月曜日~土曜日祝日営業)
各種お手続きに関する窓口:0120-50-9431
9:30~17:30(月曜日~土曜日祝日営業)
そのほか、下記のコープ共済連ホームページをご覧ください。
詳細はここから⇒コープ共済連HP
老後資金は2000万円必要?②
老後資金がいくら必要か計算する前に、まず次の内容について考えてみてください。それは、「どこで」「誰と」「どんな風に暮らすのか」と言うことです。それによって必要な老後資金は全く違います。考える時のポイントを紹介します。
①どこで
ポイント:住み替えをするかどうか?
例えば:今と同じ家で/ふるさとに帰って/住みたい別の場所で/一戸建てからマンションへ/元気なうちに高齢者住宅へ
②誰と
ポイント:いずれは一人?
例えば:ひとりで/夫婦で/親と、または子どもと/友だちと
③どんな風に
ポイント:年金以外の収入が何歳まであるか?
例えば:収入のある仕事をしっかりする/収入のある仕事を少しする/収入が伴わないボランティア活動をする/趣味を楽しむ/のんびり暮らす
①から順番に自分の希望を当てはめてみるとイメージが具体的になります。シングルの方は自分で考え、夫婦ならお互いの希望を話し合うところから始めます。日本は世界でも有数の長寿国ですから、老後も長くなっています。元気で仕事もできる60代、70代。さらに介護が必要になる可能性が高くなる80代、90代。全ての年代で上記について考えてみましょう。人生計画通りに、と言うわけにはいきませんが、平均寿命までは生きるとして考えてみることが大切です。
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
NPO法人Wco.FPの会は、おもに生活クラブ生協の組合員対象のライフプラン講座の企画、講座の講師派遣、および個人相談の三つの事業を中心に活動しています。
NPO法人Wco.FPの会のホームページがリニューアルされました!⇒こちら
ライフプラン講座メニュー⇒こちら
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「世代も超えて、地域をつくる共済をつくりましょう」です。
たすけあいの消費材である「生活クラブ共済ハグくみ」をはじめ、子どもへの将来の保障など、おすすめのポイントを紹介しています。
さらに、東京・神奈川の組合員限定の所得保障共済を新たに取組みます。
掲載記事はこちら⇒たすけあいカタログ20年4月号
生活クラブ共済ハグくみホームページリニューアルのお知らせ
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび、生活クラブ共済連ホームページ内にある、生活クラブハグくみのホームページを、より使いやすく快適にご利用いただけるようにページ構成やビジュアルをリニューアルしました。
今回のリニューアルでは、スマートフォンやタブレット等の端末からも見やすくなっております。
今後とも、より利便性の高いホームページをめざしてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。
ここをクリック⇒ハグくみHP
老後資金は2000万円必要?①
2019年、「老後資金が2000万円必要」という金融審議会ワーキンググループの報告書が大きな問題になりました。2000万円という数字だけが独り歩きしてしまいましたが、報告書では、根拠となる考え方、資金の必要性が記載されています。そして「暮らし方は様々なので、不足しない人もいるが、これまでより長く生きる以上、今までより多くのお金が必要になってくる。長寿の時代では、今後の資産形成や資産寿命を伸ばすことが必要」とまとめられています。
総務省の家計調査※では、高齢無職世帯の家計において、高齢夫婦世帯で毎月平均4万円以上の赤字、高齢単身世帯で平均3万円以上の赤字と記載されています。「年金生活の家計は赤字」という統計は、ここ数年で大きく変化していません。今回、国の報告書で具体的な金額が出たことにより不安が大きくなったのかもしれません。
では、実際に老後資金はいくらあれば安心なのでしょうか?実は答えはありません。「暮らし方は様々なので」とあるように、皆さん一人一人必要な額は違います。ただ漠然といくらあれば良いのだろう?と考えるのではなく、「自分は?我が家の場合は?」と、具体的にイメージして考えることが重要です。
次回から少し具体的な考え方をお知らせしていきます。
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
※関連データ:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2018年(平成30年)家計の概要」より
上記リンク先⇒Ⅱ 総世帯及び単身世帯の家計収支
NPO法人Wco.FPの会は、おもに生活クラブ生協の組合員対象のライフプラン講座の企画、講座の講師派遣、および個人相談の三つの事業を中心に活動しています。
ホームページ⇒NPO法人Wco.FPの会
ライフプラン講座メニュー⇒2019年度ライフプラン講座
【CO・OP共済ニュース】
日頃よりCO・OP共済をご利用いただきありがとうございます。
厚生労働大臣が定める先進医療は、随時、対象とする医療技術等について評価・見直しがされますが、2020年4月1日以降、先進医療より「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」が外れることになりました。
1.先進医療の見直しについて
先進医療とは、厚生労働大臣が定めた先進的な医療技術のことです。
厚生労働省では、先進医療について、将来的に保険診療(健康保険等、公的医療保険制度の適用となる診療)とするかどうかの評価を行なっています。そのため、先進医療の対象となる医療技術等も、随時、評価・見直しが行われます。
2.先進医療共済金のお支払いについて
「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を受けた場合の共済金のお支払いについて、詳しくはCO・OP共済ホームページ(※)をご覧ください。
※こちらをクリック⇒【ご契約者の皆様へ】「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」の先進医療からの除外について
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブの情報誌です。
特集は「暮らしのリスクに備える」です。
保障を選ぶ時のポイントや災害への備えなどを紹介しています。
掲載記事はこちら⇒たすけあいカタログ20年2月号
こころの病気になった時に私的保障~就業不能保障~
「こころの病気」(精神疾患)で入院した場合、民間の医療保障に加入していれば給付が受けられる場合があります。精神疾患は、長期入院になる可能性が高いため、医療保障は一定の備えになると言えます。
一方、「こころの病気」は、入院をともなわない治療も多く、通院や自宅療養になった場合は、医療保障からの給付は対象外となる場合もあります。さらに仕事ができず収入がダウンすると、家計にも影響が出てきます。そのような時の備えとして「就業不能保障」があります。この保障は、病気やケガにより一定期間働けなくなった時に、毎月一定額(例えば10万円/月など)の給付が受け取れるというものです。
しかし、「就業不能保障」には注意が必要です。長期療養になる可能性が高いのは、精神疾患、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、交通事故や不慮の事故の3つですが、精神疾患は保障の対象外である場合もあります。たとえ対象でも、給付の支払い条件が厳しく設定されていることがあります。
今後、保障範囲がひろがる可能性もありますが、精神疾患が増えている中、割安の保険料(掛金)で充実した保障を得るのは難しいと考えます。あくまで民間の保障でカバーできる範囲を知った上で、必要に応じて検討するほうがよいでしょう。
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
共済と保険の情報を掲載した、生活クラブ共済連の情報誌です。
特集は、「家計にやさしく、福祉も広げる「共済」」です。
共済でお支払いを受けた組合員の声より、家計に役立った事例が紹介されています。
また、生活クラブグループの福祉事業が年々地域で広がり続けています。
掲載記事はこちら⇒たすけあいカタログ20年1月号
うつ病などで仕事ができなくなった時の保障②
前回は「こころの病気」(精神疾患)になった時の公的保障を紹介しました。今回は民間の生命保険などの私的保障を紹介します。
入院保障がある医療保険などに加入している場合は、治療のため入院すれば「入院給付金」がもらえます。金額や支払い条件は、契約している保障内容を確認してください。契約証券には入院日額(入院1日あたりの給付額)、1入院支払限度日数、通算限度日数などが記載されています。具体的には給付例を参照してください。
【保障内容 1日5,000円、60日型の場合の給付例】
(例1)70日入院した場合⇒5,000円×60日=300,000円
(例2)30日入院して退院、50日後に再び40日入院⇒5,000円×60日=300,000円
※退院して次の入院まで180日以上あいていないので、30日と40日は1回の入院とみなす)
(例3)30日入院して退院、200日後に再び40日入院⇒5,000×30日+5,000×40日=350,000円
※退院して次の入院まで180日以上あいているので、それぞれ1回の入院とみなす)
「精神および行動の障害」での平均入院日数は277.1日で、「神経系の疾患」81.2日、「循環器系の疾患」38.1日より格段に長くなっています(※厚生労働省 平成29年「患者調査の概況」より)。こころの病気の場合は、長期療養が必要になる例が多いのですが、入院をしない治療も多いため、保険で備えるには限界があることも知っておきましょう。
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
※参照:厚生労働省HP「平成29年(2017)患者調査の概況」→こちら
うつ病などで仕事ができなくなった時の保障
近年大幅に増えているのが「こころの病気」(精神疾患)です。平成29年には患者数が400万人を超えており、誰もがかかる可能性があると言えます。今回は、こころの病気になった時の公的な保障について紹介します。
病気は、適切な治療が必要です。治療費は健康保険の対象であれば、自己負担は3割です(70歳未満の人)。さらに負担が高額になった場合は、1か月の上限額があります。また長期通院が必要になった時は、「自立支援医療制度」(精神通院医療費の公費負担)があり、医療費が軽減されます。対象は「すべての精神疾患」で、申請は市町村の窓口です。
仕事をしている場合は、入院や自宅療養などで休職をすると収入がダウンしてしまいます。そのような時の所得保障として「傷病手当金」があります。これは健康保険の制度で、期間は最長1年6か月です。ただし自営業などの方が加入する国民健康保険にはありません。所属する健康保険で違いがありますので確認してみましょう。
国はメンタルヘルスに積極的に取り組んでいます。地域には、市町村役場や保険センターなど複数の相談窓口があります。こころの病気になってしまった場合には、事情に応じて早めに相談し、必要な支援をうけて回復をめざしましょう。
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
参考:厚生労働省HP「みんなのメンタルヘルス」→こちら